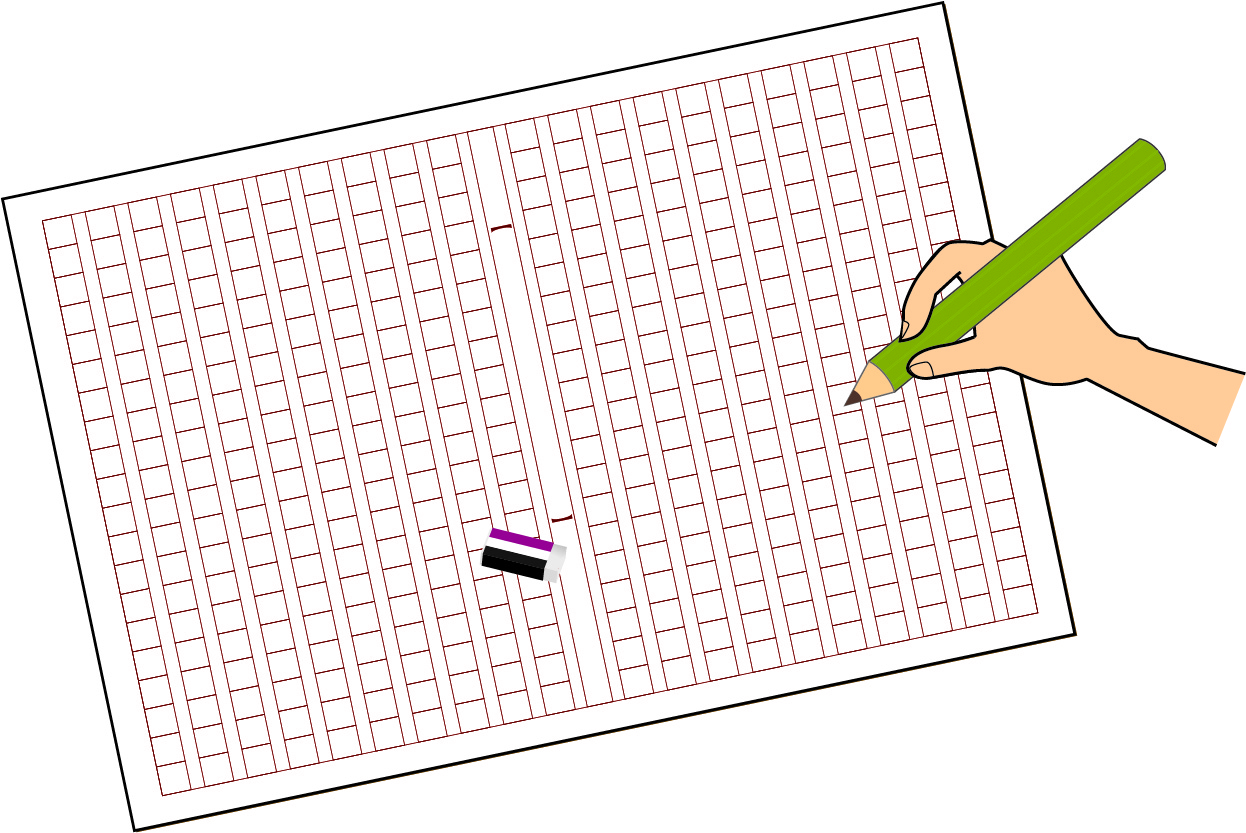「修学旅行の感想文、全然書けないって言ってるんです…」
そんな声、よく聞きます。お子さんが原稿用紙を前にして手が止まっている姿を見ると、親としても何か手伝ってあげたくなりますよね。
でも、「どう声をかけたらいいの?」「どこまで手伝っていいの?」と悩むことも多いはずです。
この記事では、感想文がなかなか書けない中学生のために、親御さんができるサポート方法をわかりやすくまとめました。
「書かせる」のではなく「引き出す」ことを意識すれば、自然とお子さんの言葉があふれてきます。
親子でできる“質問テンプレート”や“失敗しない声かけ例”、さらには「書けないときの奥の手」までご紹介。
感想文は、子どもにとって思い出を振り返り、気づきを言葉にする貴重な学びの機会。
うまく書かせることが目的ではなく、“気づく体験”を一緒にサポートしてみませんか?
この記事が、お子さんとの会話がより自然に生まれるヒントになれば嬉しいです。
子どもが感想文でつまずく理由とは?
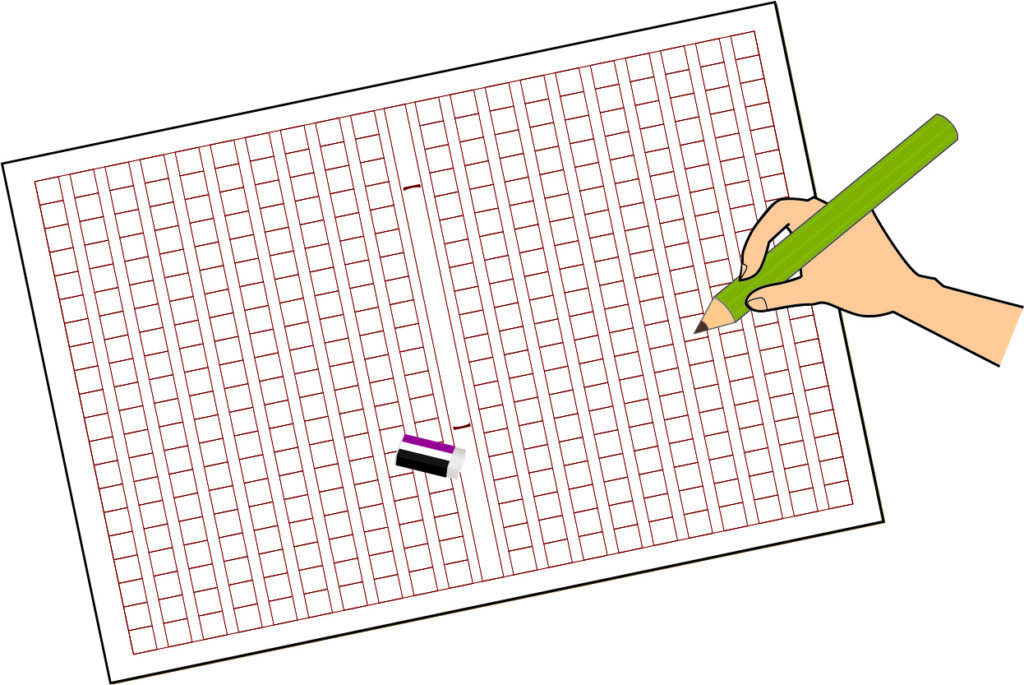
「何を書いていいかわからない」「何も覚えてない」
——こうした言葉に困惑した経験はありませんか?
実は、感想文が書けない原因の多くは「記憶があいまい」または「感情と言葉を結びつけるのが苦手」というケースがほとんどです。
中学生にとって“感じたこと”を“言葉にする”のは簡単な作業ではありません。
特に思春期は、自分の気持ちをうまく表現できず、もどかしさを感じることもあるでしょう。
そのため、親としては「まず話す場をつくってあげる」ことがとても大切です。
日常会話の延長として、「どんなことがあったの?」「どんな場面が印象に残ってる?」といった声かけをしてあげると、お子さんも自然に話し始めることができます。
感想文は、そうした会話から生まれる“心の動き”を形にしていくもの。
親のサポート次第で、子どもの気持ちがスムーズに言葉としてあらわれてくるのです。
感想文の基本構成を知っておこう(親の理解用)
感想文は、「出来事+気づき+学び」の3つで構成されるとスムーズです。
この流れを親があらかじめ理解しておくと、サポートの際に非常に役立ちます。
- 出来事:印象に残った体験(例:奈良の大仏を見た)
- 気づき:その時の感情や考え(例:昔の人の知恵と努力に驚いた)
- 学び:それをどう活かしたいか(例:歴史にもっと興味を持ちたい)
このように構成を明確にすると、お子さんの頭の中も整理されやすくなります。
「じゃあ、そのときどう思ったの?」
「それから何を学んだ?」と、段階的に質問を投げかけることで、自然と感想文の流れができていきます。
また、文章を書くのが苦手なお子さんでも、まずは口で答えてもらい、その内容をメモして一緒に構成を考えるスタイルにすれば、スムーズに進めることができます。
文章力ではなく、感じたことを大切にするという意識を持つことが重要です。
書けない子への声かけアイデア
まずは「思い出話を聞く」ことから始めましょう。親子で写真を見ながら話すと記憶がよみがえります。
特に、楽しかったこと・驚いたこと・友達との出来事など、感情が動いた場面を中心に聞くのがポイントです。
記憶を引き出す質問例
- 一番驚いた場所はどこ?
- 友達と協力したことって何かあった?
- 家族に話したくなった出来事は?
- 先生やガイドさんの話で印象に残った言葉は?
気持ちを言葉にするサポート
「それって楽しかったの?怖かったの?」と感情を確認してあげると、お子さん自身も気持ちを整理しやすくなります。
「それってなぜ印象に残ったのかな?」と少し深掘りするのも効果的です。
さらに、「そのときの気持ちを一言で表すと?」というように問いかけると、短いながらも印象的な表現が出てくることもあります。
言葉に詰まっている子どもでも、こうした会話を通じて少しずつ気持ちが整っていくはずです。
よくある親のNG対応とベスト対応
やりがちなのが「じゃあこう書けば?」と親が文章を作ってしまうことです。
これは、お子さんの考える力を奪ってしまい、「自分の言葉じゃない」と感じてやる気をなくす原因にもなります。
ベストなのは「お話を聞く聞き役」になること。
お子さんが一文でも書けたら、「それ、すごくいい表現だね」「よく覚えてたね」と褒めてあげましょう。自己肯定感が高まり、自信を持って続きを書けるようになります。
また、感想文に正解はないということを伝えてあげるのも効果的です。
「こんなこと書いていいのかな?」と不安がるお子さんには、「あなたが感じたことなら、全部正解だよ」と安心感を与えてあげてください。
その一言が、子どもにとって大きな後押しになります。
テーマ別:親が引き出せる話のタネ例
感想文は、体験をどう切り取るかで内容がガラッと変わります。
親御さんが話題をリードすることで、より深みのあるエピソードが引き出せます。
- 友情:「友達とどんな場面で笑った?」「困った時に助けてもらった?」
- 平和学習:「原爆資料館でどんな展示が心に残った?」「どんな気持ちになった?」
- 自主行動:「地図を見ながら行動するのってどうだった?」「何が難しかった?楽しかった?」
- 文化体験:「工芸体験で上手にできた?職人さんの話で印象に残ったことは?」
こうしたテーマで会話すると、具体的なエピソードが出やすくなります。
単なる「楽しかった」だけで終わらせず、その奥にある“なぜ印象に残ったのか”を引き出してあげましょう。
もしどうしても書けないときの“奥の手”
感想文は無理に書かせるものではありません。どうしても進まないときは、次のような“補助策”を試してみてください。
親子で“質問テンプレート”に答えるシートを作る
例:
- どこに行った? → 京都・奈良
- 一番心に残ったことは? → 清水寺の景色
- なぜ心に残った? → 夕日がすごくきれいだったから
- そこから何を学んだ? → 自然と歴史の調和の美しさ
口述筆記もOK
お子さんが話した内容を親がメモして、あとで自分で清書してもらうのも一つの方法です。
「自分の言葉」で書くという目的を果たしつつ、書くハードルを下げられます。
また、「うまく言えないけど…」という言葉にもヒントが隠れていることがあります。
焦らず待ち、安心して話せる雰囲気づくりが大切です。
Q&A:親御さんからよくある質問
Q:どこまで手伝っていいの?
A:文章そのものはお子さん自身が書くのが理想ですが、内容を引き出すための会話やメモ作りはしっかりサポートして大丈夫です。
方向性を一緒に考えたり、書き出しを手伝ったりする程度なら問題ありません。
Q:感想文の文字数はどのくらい?
A:学校によって異なりますが、一般的には400〜800字程度が多いです。
あくまで目安なので、内容に深みがあれば短めでも大丈夫です。
逆に長くなりすぎた場合は、エピソードを絞る工夫をしてみてください。
Q:テーマが決まらないときは?
A:「一番話したくなること」をテーマにすれば大丈夫です。
いろいろな体験を書こうとするとかえって難しくなるので、「一番心が動いた場面」に絞って話を深めていきましょう。
まとめ
修学旅行の感想文は、子どもにとって「思い出を言葉にする」だけでなく、「自分の成長に気づく」ための大切な機会です。
しかし、文章にするのが難しいと感じる子どもはとても多く、親としても手助けしたくなる場面があると思います。
でも、手伝いすぎるのではなく、「話を聞いて引き出す」というサポートの仕方が、子ども自身の力を育てる一番の近道になります。
感想文を書く過程は、親子の対話のチャンスでもあります。
旅行の思い出を一緒に語り合う中で、お子さんの中にある“学びの芽”が自然と育っていくでしょう。
ぜひ「うまく書かせる」ではなく、「思い出を一緒に振り返る」時間を大切にしてみてください。その先に、自分の言葉で綴る、素直で温かい感想文が生まれるはずです。
お子さんの“心の記録”を支える一歩として、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。