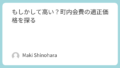新幹線に乗っているとき、急な電話がかかってきて「どこで話せば迷惑にならないのだろう?」と戸惑った経験はありませんか。
座席で通話すると周囲の視線が気になる一方で、デッキに移動すれば本当に大丈夫なのか不安に思う人も多いはずです。
実際、鉄道会社は「通話はデッキで」と案内していますが、車両や時間帯によっては「うるさい」と感じられてしまうケースもあります。
さらに、最新型のN700Sのように専用の通話スペースを設けている列車もあり、知っているかどうかで快適さが大きく変わります。
本記事では、新幹線で電話をする際に知っておきたい「通話できる場所」と「守るべきマナー」を徹底解説。
基本のデッキ利用からグリーン車での注意点、各鉄道会社のルール、さらには迷惑にならないための工夫までわかりやすく紹介します。
この記事を読めば「もう新幹線での電話マナーに迷わない」と安心でき、出張や旅行をより快適に過ごせるはずです。
新幹線で電話できる場所はどこ?デッキ利用マナーと注意点まとめ

新幹線で電話はどこでできる?
基本はデッキ(車両間のスペース)
新幹線で通話する際の基本的な場所は「デッキ」と呼ばれる車両間のスペースです。
座席エリアでは他の乗客への配慮から通話は控えるよう案内されています。
デッキはトイレや自動販売機の近くにあることが多く、音がこもりにくいため会話しても比較的迷惑になりにくいとされています。
また、デッキは乗降口に近い位置にあることも多いため、移動時に気を使う必要がありますが、短い通話を行うには最適な場所です。
車両によってはデッキの広さや人通りの多さが異なり、利用する時間帯や混雑状況によって印象が変わる点にも注意が必要です。
さらに、他の乗客が通りやすいように壁側に寄る、荷物を広げないなどの配慮も欠かせません。
こうした細やかなマナーを守ることで、誰にとっても快適に利用できる環境が保たれます。
専用通話スペースがある新幹線(N700Sなど最新車両)

一部の新型車両、たとえばN700Sなどには専用の通話スペースが設けられているケースがあります。ビジネス利用の多い東海道新幹線を中心に導入されており、防音性を高めているため、周囲を気にせずに電話が可能です。
利用可能な車両かどうか、乗車前に公式サイトや案内板で確認しておくと安心です。
こうした専用スペースはまだ限られた車両にしか導入されていませんが、今後は需要の増加に伴って拡大される可能性もあります。
利用者にとっては、落ち着いて会話ができる安心感が大きく、特に長時間の移動やビジネス利用では重宝されるでしょう。
グリーン車・指定席での通話ルール
グリーン車や指定席でも座席での通話は推奨されていません。
車掌や車内アナウンスでも「通話はデッキで」と案内されることが多く、特に静かな環境を求めて利用する乗客が多いため注意が必要です。
やむを得ず短い通話をする場合も、必ず小声で素早く済ませましょう。
さらに、グリーン車は追加料金を支払って利用する乗客が多いため、静寂や快適さを重視する人が特に多いという点も理解しておくべきです。
ちょっとした声でも不快に感じる方がいるため、できるだけデッキに移動して対応するのがマナーです。
また、ビジネス利用が中心となる時間帯や長距離の移動では、集中して作業や休養を取りたい人も多いため、より一層の配慮が求められます。
通話を避けられない場合には、事前に要点をまとめておき、必要なことだけを短く伝える工夫をするとよいでしょう。
新幹線での電話マナー
声の大きさと通話時間の配慮
デッキであっても大声や長電話は周囲に迷惑をかける可能性があります。
要点だけを伝えて短時間で終えることが理想です。特にビジネス会話やプライベートな話題は、声が響きやすい環境で聞かれやすいため注意が必要です。
さらに、周囲に他の乗客が立っている場合には会話の内容が思った以上に聞こえてしまうこともあり、情報漏洩のリスクやプライバシー面でも気を付ける必要があります。
静かな声で話すことに加え、あらかじめ話す内容を整理し、最小限の時間で済ませる工夫をすると安心です
声量を意識して抑えることはもちろん、話し方も落ち着いたトーンを心掛けると周囲に与える印象が大きく変わります。
スピーカーフォンやビデオ通話はNG
スピーカーフォンやビデオ通話は周囲に内容が筒抜けになり、非常に迷惑がられます。
必ずイヤホンやハンズフリーを避け、受話スタイルでの利用を心掛けましょう。
さらに、ビデオ通話は画面の明かりが周囲に目立つ場合もあり、夜間などでは特に不快感を与える恐れがあります。
どうしても利用しなければならない状況がある場合でも、新幹線車内では控え、駅の待合室や到着後に行うのが無難です。
混雑時や深夜早朝の利用に注意
混雑時のデッキは乗客の移動も多いため、電話が邪魔になってしまうことがあります。
深夜や早朝も静かな環境を保ちたい乗客が多いため、特に注意が必要です。
こうした時間帯は小さな物音でも目立ちやすく、周囲の乗客の休息を妨げてしまうことがあります。なるべくメールやメッセージで代用する、あるいは通話を数分以内に収めるなど、より一層の気遣いが求められます。
迷惑行為になりやすいケース
客室での通話が嫌がられる理由
座席での通話は周囲に声が響きやすく、集中して休みたい人や仕事をしている人にとって大きなストレスになります。
そのため鉄道会社も公式に「通話はデッキで」と呼びかけています。
特に長距離移動では、仮眠や読書、パソコン作業をしている人が多く、わずかな会話の声でも気になることがあります。
新幹線の車内は密閉性が高く音が反響しやすいため、思った以上に声が広がってしまう点も注意すべきポイントです。
座席での電話がマナー違反と見なされるのは、こうした環境的要因も大きいのです。
デッキでも「うるさい」と思われる場面
デッキだからといって安心できるわけではありません。
長時間通話を続けたり、複数人で会話したりすると、やはり「うるさい」と感じる人もいます。
特に移動中に人が行き来するデッキは静けさを確保しづらいため、大きな声は目立ちます。
また、ビジネス通話や私語で盛り上がっていると、近くを通る人に不快な印象を与えることも少なくありません。
通話は必要最低限に留め、数分で切り上げるようにするのが無難です。
長電話・仕事の会話に注意
ビジネス通話は声が自然と大きくなりがちです。
また内容がセンシティブな場合もあり、公共の場での通話は避けるのが望ましいでしょう。
さらに、長時間の会話は情報漏洩のリスクや、周囲への迷惑につながりやすい点も懸念されます。
必要に応じて駅に着いたタイミングで折り返す工夫が大切です。
加えて、どうしても重要な電話を受ける場合は、要点をメモにまとめてから会話すると短縮でき、周囲への配慮にもつながります。
新幹線のデッキでの電波状況
電波が通じる場所の見極め方
新幹線の電波状況は、場所によって大きく異なります。
特にトンネル内や山間部では、携帯電話の電波が途切れやすいため、通話をする際は、なるべく都市部や駅の近くなど、電波が安定している場所を選ぶと良いでしょう。
また、携帯キャリアによって電波の届きやすさが異なるため、利用するキャリアの電波状況を事前に調べておくと安心です。
最近では、新幹線の車内Wi-Fiを活用することで、インターネット通話(VoIP)を利用する方法もあります。
電話スペースの利用方法
一部の新幹線では、デッキの一角に電話専用スペースが設けられています。
ここを利用することで、より静かに通話を行うことが可能です。
乗車前に、新幹線の設備を確認し、適切なスペースを利用するようにしましょう。
また、電話専用スペースがない場合でも、なるべく人の少ないデッキを選んで通話することで、周囲への影響を最小限に抑えることができます。
新幹線ごとの違いと最新事情
JR東海(東海道新幹線)の方針
東海道新幹線ではビジネス利用者が多いため、特にデッキでの通話マナーが強調されています。
最新車両では専用スペースの設置も進んでおり、通話ニーズに対応した設備が整備されています。
さらに、東海道新幹線ではビジネスパーソン向けの「車内ワーク環境整備」の一環として、静かな車内を維持する取り組みが強化されています。
そのため、通話をする場合は他の乗客の快適さを損なわないよう、特に配慮することが求められています。
アナウンスやポスターでも繰り返し注意喚起が行われており、実際に車掌がマナー違反を指摘するケースもあるほどです。
JR東日本・西日本のマナー啓発例
東北新幹線や山陽新幹線でも基本的に「デッキで通話」がルールですが、公式サイトやアナウンスで繰り返し周知されているのが特徴です。
各鉄道会社が共通して「座席での通話は控える」ことを強調しています。
さらに、近年は公式SNSや動画による啓発活動も行われており、若い世代にもマナーを浸透させる工夫がされています。
観光客の利用が多い季節や大型連休前には、特別なキャンペーンとしてマナー啓発が強化されることもあります。
海外の高速鉄道との比較
海外の高速鉄道では通話に関するルールが緩いケースもあります。
しかし日本では「静けさ」を重視する文化が強いため、マナー意識が高く求められています。
特にヨーロッパの一部路線では車内で普通に通話している光景も見られますが、日本の新幹線ではこれが大きな違和感を与える場合があります。
逆に言えば、日本ならではの「静かに移動できる安心感」が新幹線の大きな魅力であり、訪日観光客にとっても高く評価されている要素のひとつなのです。
快適に利用するための工夫

メッセージアプリやメールで代替
短い内容であれば、電話ではなくメッセージやメールで連絡するのがおすすめです。
公共の場での通話を避けられるため、マナー面でも安心です。
さらに、メッセージであれば相手が自分のタイミングで確認できるため、急ぎでない内容を落ち着いて伝えられるメリットもあります。
添付資料や写真を送れる点も便利で、誤解を防ぐ効果もあります。
駅ホームや到着後にまとめて連絡する方法
どうしても伝えたい内容がある場合は、到着駅のホームや改札を出てから連絡するという工夫も効果的です。
相手への配慮と自分の安心感を両立できます。
また、駅構内には待合室やベンチなどもあるため、落ち着いて話せる場所を選ぶことでより快適に連絡できます。
特に長距離移動後は休憩も兼ねられるため、相手との会話にも余裕が生まれるでしょう。
状況によっては次の乗り換えまでの時間を利用するのも賢い方法です。
ノイズキャンセリングイヤホンを活用
もし周囲の騒音で相手の声が聞き取りにくい場合は、ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンを使用すると快適です。ただし、自分の声は必ず控えめにしましょう。
さらに、通話相手の声が聞きやすくなる分、つい声量が大きくなってしまうことがあるため、意識的に落ち着いた声で話すことが大切です。
イヤホンを使うことで周囲の人への音漏れを防ぎやすくなる利点もありますが、公共の場である以上、短時間で切り上げる配慮は忘れないようにしましょう。
まとめ:新幹線での電話は「デッキ利用+マナー」が基本ルール
新幹線での通話は「デッキ」が基本の場所であり、座席では避けるのがマナーです。
声の大きさや通話時間に注意し、周囲に配慮することが快適な移動につながります。
鉄道会社ごとにルールや専用スペースの有無が異なるため、乗車前に確認しておくことも大切です。特に長距離移動や出張の際には、短い時間でも他の乗客への影響が大きくなるため、より慎重な姿勢が求められます。
近年は外国人観光客の増加もあり、文化の違いによるマナー意識の差が指摘されることもありますが、日本の新幹線では「静けさを守ること」が大切なルールであると周知されつつあります。
旅行や出張を気持ちよく過ごすために、ぜひマナーを意識して利用しましょう。
さらに、個々人のちょっとした心がけが全体の快適さにつながり、結果として「また新幹線に乗りたい」と思える体験を作り出すことにもなるのです。