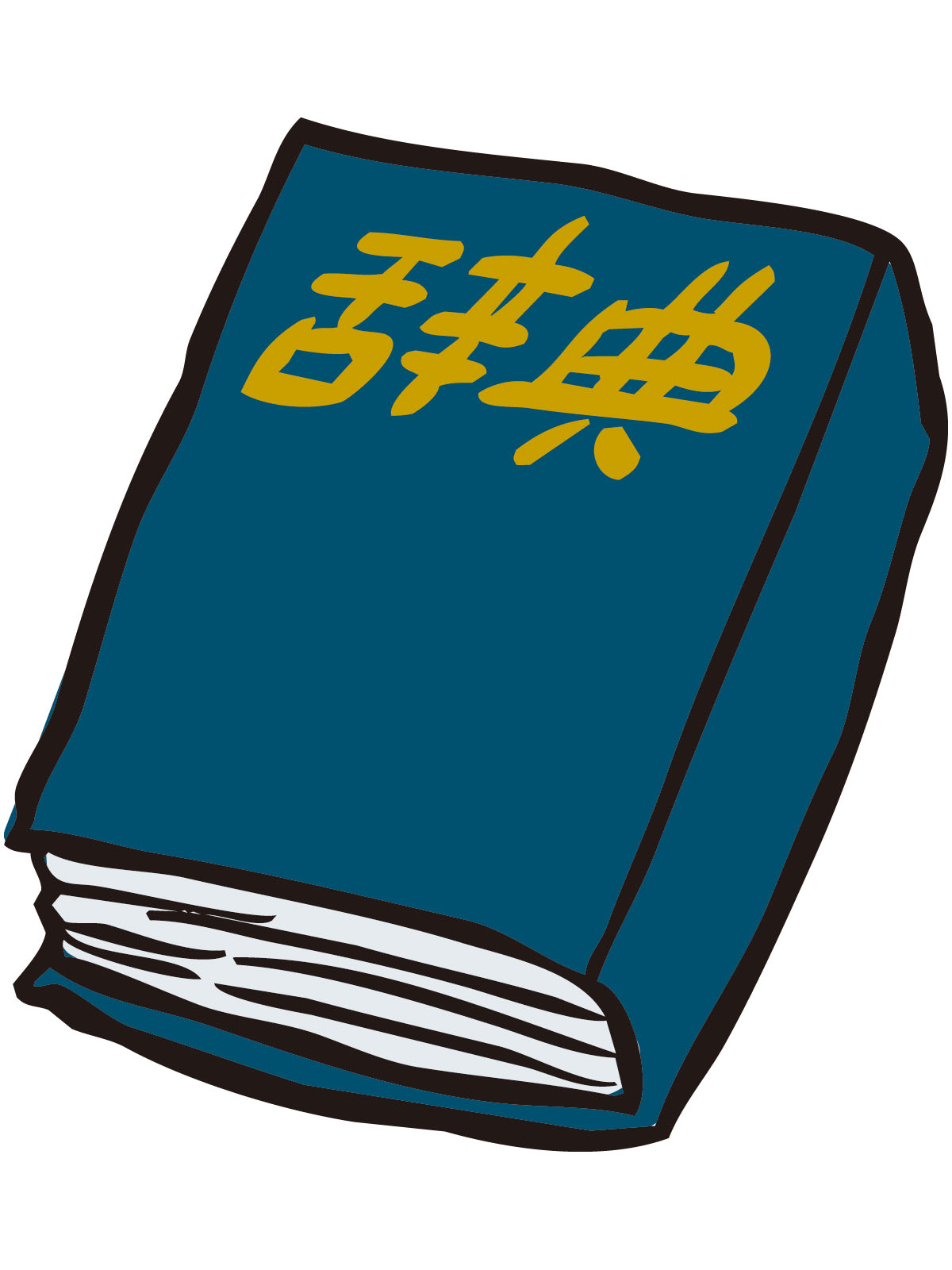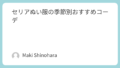自らが学んだ筆順と現在子供たちが学んでいる筆順が異なることに驚かされることがあります。
自分は正しいと教わった田の筆順現在では筆順が変更されたという話という情報は知りませんでした。
果たして、筆順は実際に変更されたのでしょうか?
漢字の筆順基準について
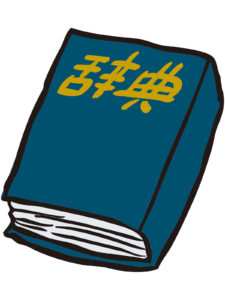
実際、漢字の筆順には基準となる書籍が存在します。
この話の発端は、家族間で意見が分かれた漢字「田」に関するものでした。
私が提案したのは、三画目に中央の縦線を引き、「土」の字を形成する筆順です。
田の書き方(過去)
一方、子どもたちが学んだ方法は、三画目に中の縦線を引いた後、横線を二本書くというものでした。
田の書き方(現在)
基準書をもとに、どちらの筆順が正しいのか明確にしましょう。
筆順指導のガイドライン
漢字の筆順に関しては、昭和33年に文部省から出された「筆順指導の手引き」という指南書があります。
この書籍は、教育漢字において一文字ごとに筆順を統一し、理解しやすくするための原則を設けています。
【基本原則1】 上から下へ書く(例: 三)
【基本原則2】 左から右へ書く(例: 川)
これらの基本原則は、私が小学校で習ったこともあり、どの世代にも共通のものです。
【原則1】 横線を引いた後に縦線を引く(例: 十)
私の筆順が正しいのではないかと思っていました。
しかし、ちょっと待ってください。
【原則2】 原則1の例外として横線が後にくる場合(例: 田)
例外?「田」は例外だったのですね。
筆順指導の疑問点
ここで一つ疑問が湧いてきます。
「田」の字の筆順についてだけでは、単に私の記憶が曖昧なのかもしれませんが、
子供たちとの会話で、彼らが学んでいる他の漢字の筆順も異なっていることが分かりましたし、
ネットで情報を調べてみたところ、私たち親世代の多くからも自分たちが学んだ筆順と現在の筆順が違う!
との声が上がっていました。
「一文字に一つの筆順」という原則があるのならば、文部省さん、一つの漢字に対して二つ以上の筆順が存在しないと考えて良いのではないでしょうか。
では、なぜ基準書があるにも関わらず、私たち親世代は異なる筆順を学んだのでしょうか?
昭和33年に発行された基準書に記されている筆順を、なぜそれ以降の世代である我々が知らないのでしょう?
また、現在の子供たちがその基準書通りに学んでいるのも奇妙な話です。
果たして昭和33年に発行された基準書の内容が、現在のものと異なっていたのかもしれませんね。
書き順の違いについての世代間のギャップ
親の世代と現在の子供たちの世代で異なる書き順を学んでいる現象の根底には、「筆順指導の手引き」が関係しているようです。
この「筆順指導の手引き」は発行以来、内容が一切変更されていないにもかかわらず、なぜ昭和33年に発行された基準書が現代の子供たちの書き順に影響を与えたのでしょうか?
「筆順指導の手引き」の普及が遅れた
昭和33年に文部省が発行した「筆順指導の手びき」は、当時は強制力がなく、広く普及するには時間がかかりました。
この結果、手引きが広まる前に教育を受けた世代は従来の書き順を学び、地域や教師によって異なる書き順で教えられていたことが多かったようです。
しかし平成に入ると…
教育現場で「筆順指導の手引き」が正しい書き順として普及し始めたことで、この手引きに基づく書き順を学んだ現代の子供たちと、それ以前の世代との間で書き順に違いが生じています。
書き順が変わったわけではなく、教育の普及の遅れによるものです。
結果として、平成以降に学んだ書き順がより正確とされる可能性が高いと言えるでしょう。
筆順は必須ではない?
驚くべきことに、「筆順指導の手引き」には「筆順を厳密に守る必要はない」という記述が含まれています。
筆順が厳格なルールではなかったんですね!
筆順を統一しようと作られた基準書が、「絶対にこの通りにしなければならないわけではない」というやや曖昧な表現をしているのは、その普及が遅れた一因かもしれません。
それにもかかわらず、試験で筆順が問われるのはどうしてでしょうか。
例えば「漢字検定」では、特定の級で筆順が問題として出されます。
テストの答えに「筆順は規則ではないため、答えは存在しない」と書くべきか、という冗談を言いたくなる気持ちもわかりますが、学んだ筆順を守ることが大切です。
それは、筆順には何らかの理由があるからです。
筆順の存在理由は何か?
筆順が「決まり事ではない」にもかかわらず存在する理由は何でしょうか?
文字を美しく書くため
筆順の一つの根拠は、文字を美しく見せる手段としての役割です。
例えば、「必」という文字の筆順はどうでしょう。
過去には「心に帯をかける」と教えられ、「心」を先に書いてから「ノ」を加える方法が一般的でした。
しかし現在の筆順は、中心の点を最初に書き、次に「ノ」を加える方式に変わっています。
これは、「心」を書いた後では中心の点がずれてしまうため、よりバランスの取れた美しい文字を目指して筆順が変更されたのです。
他にも、「書」という文字について考えてみましょう。
昔は「日」の上の横線をすべて書いた後に、最後に縦線を加える書き方が一般的でしたが、現在は横線を均等に配するためにその順番が変更されています。
これらの変更は、文字が全体として均整が取れ、見た目に美しく見えるようにするための工夫です。
筆順は固定されたルールではない?
「筆順指導の手引き」によると、筆順は「絶対にこの方法で書かなければならない」という硬い規定ではないようです。
実は筆順は、決められた規則ではなかったんですね!
筆順を標準化する目的で作成された基準書が、「必ずしもこの方法で書く必要はない」と柔軟な姿勢を見せていますが、これが普及しなかった理由も理解できます。
それにもかかわらず、筆順がテストで問われることがあります。
「漢字検定」の試験では、特定の級で筆順が問題になっています。
試験の答えに「筆順は規定ではないため、正答は存在しない」と記載すれば良いのでしょうか?
なんて考えることもありますが、やはり学んだ筆順を守るべきでしょう。
それには、筆順が存在するには何かしらの理由があるからです。
筆順の存在理由とは?
筆順が「決まりではない」とされてもなお存在する理由は何でしょうか?
文字を美しく表現するため
筆順は、文字を美しく見せるための手段としての重要な役割があります。
たとえば、「必」という文字の筆順を見てみましょう。
伝統的には「心に帯を掛ける」形で、「心」を先に書いて最後に「ノ」を加える方法が多かったです。
しかし、現在の一般的な筆順は、最初に中心の点を置き、次に「ノ」を書く方法に変更されています。
これは、「心」を書いた後に中心の点を加えると、位置がずれやすいため、より均整の取れた形で文字を表現するための変更です。
また、「書」という文字の例もあります。過去には「日」の部分の上にある横線を書いた後、縦線を4画目に加える方法が一般的でしたが、現在は全ての横線を書き終えてから最後に縦線を加えることが推奨されています。
この方法では、横線間の間隔を均等に保つことができ、全体として美しく整った文字が書けるため、この順序で書くことが推奨されています。
文字の機能性と筆順
筆順が決められる際には、文字を書く上での機能性が重視されています。これには「速く書けること」と「読みやすくすること」が含まれます。
どのように筆を運べば効率的に速く文字を書けるか、また読み手にとって解読しやすい文字形になるかが考慮されて筆順が設定されています。
さらに、独自の筆順、つまりクセ字は読みにくいため、統一された筆順を学ぶことで、「この文字は何と書いてあるのか」という混乱を避けることができます。
草書体と筆順の関連
特に「田」の字の筆順は例外的な扱いを受けており、これには草書体との関連が深いです。
通常、「十」は横線を先に書きますが、「田」に含まれる「十」の場合は縦線が先です。
これは、草書で「十」を「〆」のように書くことから、その筆順を楷書にも反映しているためです。
「王」や「生」などの文字も同様に、草書の影響を受けた筆順が採用されています。
将棋の駒に書かれた「王」の草書体を見れば、縦線から始める理由が理解できるでしょう。
実は、草書は楷書よりも先に成立しており、その後行書、楷書の順で発展していきました。
そのため、草書の筆順が現代の筆順に影響を与えているのです。
まとめ
昭和33年に発行された「筆順指導の手引き」は、筆順の統一を図るために作られましたが、この基準書が厳格なルールとして受け入れられたわけではありません。
筆順が存在する理由としては、読みやすさや美しさが挙げられます。
私が若い頃勤めた会社の名物社長は書の達人で、彼の書く文字は絵のように美しかったことを覚えています。
社長は政治家の秘書を経て、自ら独学で書を学んだ人物でした。
彼のように、筆順を意識せずとも美しい文字を書ける技術を持っていたのかもしれません。